今日は日本の漁業について書いていく。
参考本は「魚も漁師も消えゆく日本」
まず前提として「人口論」も言っているようにその国の豊かさは第一次産業で測れると思っている。
食料の余剰分で第二産業、第三産業ができていくため、第一次産業の発展無しにあとが栄えるとは思えない。
なにより第一次産業、農業や漁業、林業など自然から資源を頂くような仕事が今の日本は深刻だ。
そもそも日本の高度経済成長を支えていたのは人口増加もあるかもしれないが、それを支える豊富な資源や
第一次産業が大きく栄えていたのがあると思う。質の良い食料が溢れるほど獲れていたが、取りすぎと
管理不足で枯渇していてどの地域も貧しくなっている。
その中でも特にひどい漁業の状態を取り上げる。
今日本の中では魚が減ったと言われる。
昔の日本1980年代の水揚げ量は1200万トンで世界一位だったそうだ。2020年では400万トンとなっており1/3に落ちてしまっている。その原因としてよく言われるものは、海水温上昇、外国船による漁獲、海の変化、クジラによる食害がある。
だが、これらは本質ではない。海水温上昇に関しては世界的に上がっているもので、むしろ他の水域の方が上がっているらしい。世界で唯一日本だけが水揚げ量が年々減少している。
そもそも海水が上昇すると何がだめなのか?
海面付近の水と深層部の水が混ざらなくなりプランクトンが減少するためそれを食べる餌の総量が減っていくため必然に魚が減っていく。
では、世界の中では日本の漁業はどう見られているのか?
めっちゃ冷ややかに見られているとのこと。SDGsの動きやMSY(最大持続生産量、魚を減らさずにとり続けられる最大値)の動きがあり、全世界で資源を守っていかないとマジでやばいってなっている中で日本は目標を全然達成していないし達成する気もない様子なので、世界から怒られていそう。
それもそのはず、一番あほだと思ったのは、日本では幼魚も漁獲してしまうとのこと。
これを聞いた時に頭悪すぎないかい?って思ってしまった。将来の資源もかすみとってしまうためそりゃあ次の世代が育たないから魚が減るよね。至極当然なことだよね。しかもその幼魚は養殖の餌となっているとのこと。
あほすぎて何がしたいのが全然わからない。そんな中漁業でうまくいっているノルウェーはどうか?資源状況に悪影響を与えてしまうし価格も低いから幼魚は捕らないとのこと。そりゃあそうだよね。日本があほすぎて普通の思考が頭いいように見えてきてしまう。そこでノルウェーについてもう少し見ていきたい。
今水産物の輸出で世界第二位のノルウェー。日本の漁業法が2018年に改正される際にも参考された国とのこと。ちなみに世界第一位は中国だが、実態はほとんどが怪しい中身の実質の第一位はノルウェーだと思っている。
さらにノルウェーの調査によると99%の漁業者が今の状況に満足しているとのこと。同じ調査を日本でしたら悲惨そうだなぁ。ノルウェーとの大きな違いは水産資源を管理して持続的に活用できているかどうかという点である。
ノルウェーも乱獲していた過去がある。昔から水産業が豊かであり土地で1816年に世界で最初の漁業に使われる糸や網の明確なルールが定められた。当時はゴールドラッシュのように漁業がおこなわれており、党技術よりも生まれてくる量の方が大きかったためどんどん獲られていった。だが、そこにアメリカ産の巻き上げ網が導入されるとそのバランが崩れてしまい、海の中を空っぽにしてしまった。その経験から国単位ですべての漁業に対して水揚げ量を厳しく報告するようになった。また、適正な大きさの魚であり販売可能なものであることを保証しなければない状態となり、小さな魚を取らないように試行錯誤されて漁具の改善がされた。また、漁獲枠というものが設けられ、実際に漁獲できる量よりもかなり少なく設定されているため、価値の低い小型の魚は決して狙わなくなる。
これらを聞いてとても賢いなぁと思った。生まれてくる以上に獲らないように厳しく規制し管理していくことで自然とバランスを保っていくこの姿勢がうまくいっている理由だと思う。だがそんだけ厳しいと不満が出るのではと思ったが、ノルウェーの漁業者は制限を受けれいており、短期的な個々の考えや利益追求を考えずに団結していけば後により大きな全体的なものが達成できることを見通していたからだとのこと。ここらへんで一気にノルウェーのファンになった。家計がうまくいっている家庭の話を聞いて、自分の親の管理のずさんさに恥ずかしくなる感覚に近い。
対する日本はどうなのか?
今回は函館を前提に話を進めるが、ごまかしが横行しているとのこと。観光客に向けて海外の魚を高額で出していたり騙しながら商売をしているとのこと。実際に小田原に旅行しに行ったときに、小田原原産の魚ですといった雰囲気と体で海外の魚が普通に売られていた。とても衝撃的でなぜか悲しかった。
また、悪循環な仕組みがある。組合長は漁師の代表として推薦や選挙でえらばれるとのこと。つまりは漁業者に厳しい人間が選ばれることはない。トップの人がそんなんじゃあいつまでたっても変わらないよね。また漁業がおこなえる権利は土地や建物と同じようなものとなっており、地元の漁協や漁業者が優先されて与えられる。そのため閉鎖性が強く、縄張り意識が強いためいつまでも変わらない。他の国では国民共有の財産という意識があるが、日本では俺たちの海、地元の海という感覚で運用しているため外部からコンサルみたいなことができない。
そんな残念な状態の日本だが自分たちにできることは少ない。まずその状況を理解し、知ることから始めるしかない。できるだけ国産を食べることぐらいかな。もっとなにかいい方法とかあったらいいと思う。
明治時代に日本に来たヨーロッパ人は日本の豊かさに驚いたとのこと。
見る影もないほど落ち込んだ日本の漁業、はたまた経済を復活させるには何が必要なのか?
絶対に世代交代。
(サムネは好きな数学者アランチューリング)
あほすぎる日本の漁業
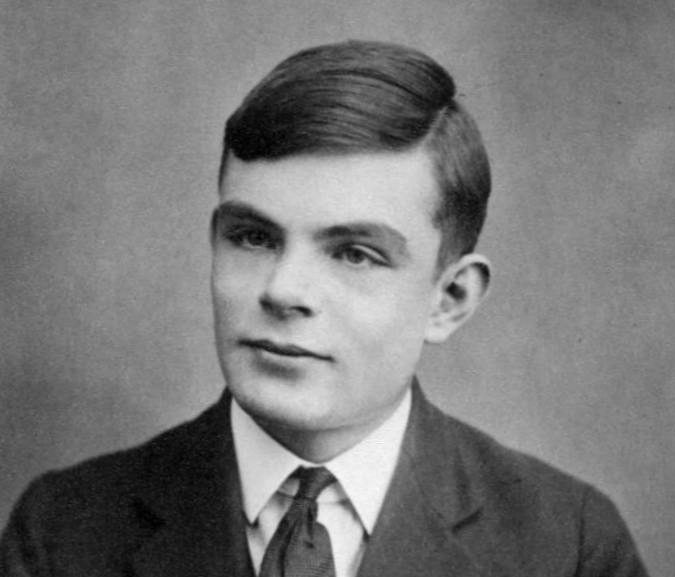 本
本
