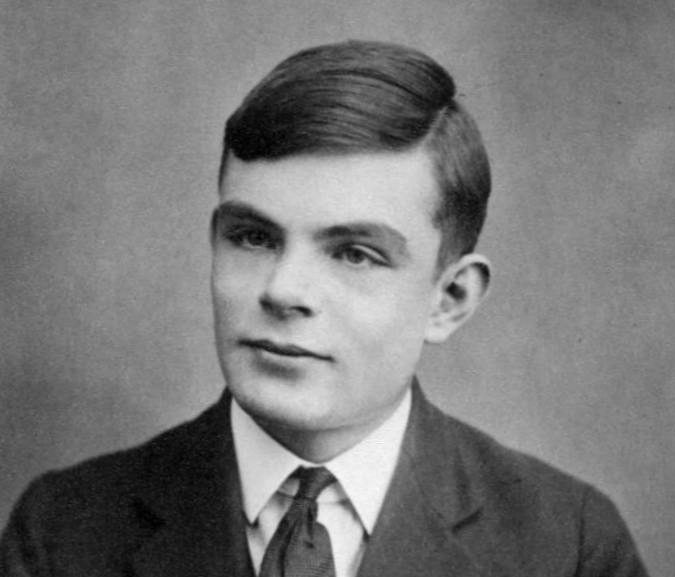今日は日本の漁業について書いていく。参考にした本は「魚も漁師も消えゆく日本」だ。まず前提として、「人口論」にもあるように、その国の豊かさは第一次産業で測れると思う。食料の余剰分で第二産業、第三産業が成り立つため、第一次産業の発展無しに他の産業が栄えるとは思えない。何より第一次産業、つまり農業や漁業、林業など、自然から資源を得る仕事が今の日本では深刻な状況にある。
そもそも日本の高度経済成長を支えていたのは、人口増加もあるかもしれないが、それを支える豊富な資源や第一次産業が大きく栄えていたことが大きいと思う。質の良い食料が豊富に獲れていたが、取りすぎと管理不足で枯渇し、多くの地域が貧しくなっている。その中でも特にひどいのが漁業の状態だ。
今、日本では魚が減ったと言われる。1980年代の日本の水揚げ量は1200万トンで世界一位だったが、2020年では400万トンとなり、1/3に減少している。その原因としてよく言われるのは、海水温の上昇、外国船による漁獲、海の変化、クジラによる食害などだ。しかし、これらは本質ではない。海水温上昇に関しては世界的な現象であり、むしろ他の水域の方が上昇しているらしい。世界で唯一、日本だけが水揚げ量が年々減少しているのだ。
そもそも海水温が上昇すると何が問題なのか?海面付近の水と深層部の水が混ざらなくなり、プランクトンが減少するため、それを食べる魚の餌が減り、結果として魚も減ってしまう。
では、世界から見た日本の漁業の評価はどうか?非常に冷ややかだ。SDGsの動きやMSY(最大持続生産量)の取り組みが進む中で、日本は目標を全然達成しておらず、達成する気もないようだ。そのため、世界から怒られている。
特に問題なのは、日本では幼魚も漁獲してしまうことだ。将来の資源も捕ってしまうため、次の世代が育たず、魚が減るのは当然だ。その幼魚は養殖の餌となっているという。ノルウェーでは、幼魚を捕らないようにしており、資源に悪影響を与えず、価格も低いため幼魚は捕らない。ノルウェーは日本よりも賢く、持続可能な漁業を実現している。
ノルウェーは水産物の輸出で世界第二位であり、日本の漁業法が2018年に改正される際にも参考にされた国だ。ノルウェーの漁業者は99%が現状に満足している。ノルウェーと日本の大きな違いは、水産資源を管理し、持続的に活用できているかどうかだ。
ノルウェーも過去には乱獲していたが、厳しい規制と管理でバランスを保っている。漁具の改善や漁獲枠の設定などにより、持続可能な漁業を実現している。これに対して、日本は観光客に海外の魚を高額で売るなど、ごまかしが横行している。
日本の漁業を改善するためには、まず現状を理解し、知ることから始めるしかない。そして、できるだけ国産の魚を食べることが重要だ。明治時代に日本を訪れたヨーロッパ人は日本の豊かさに驚いたが、現在の日本の漁業や経済を復活させるためには世代交代が必要だと思う。